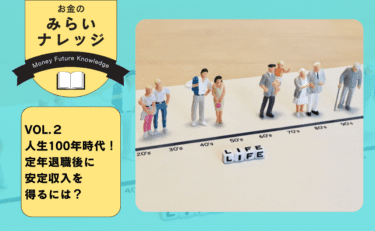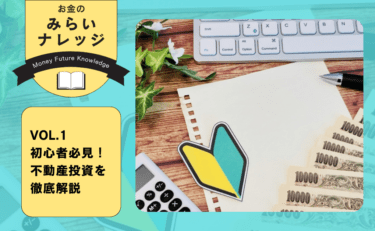2025.04.04
年金っていつから受け取る?|お金のみらいナレッジ
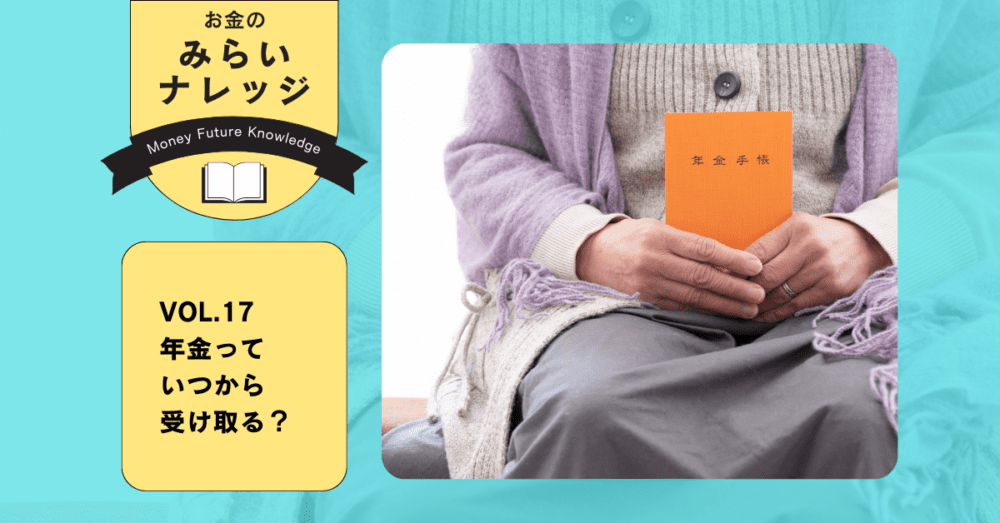
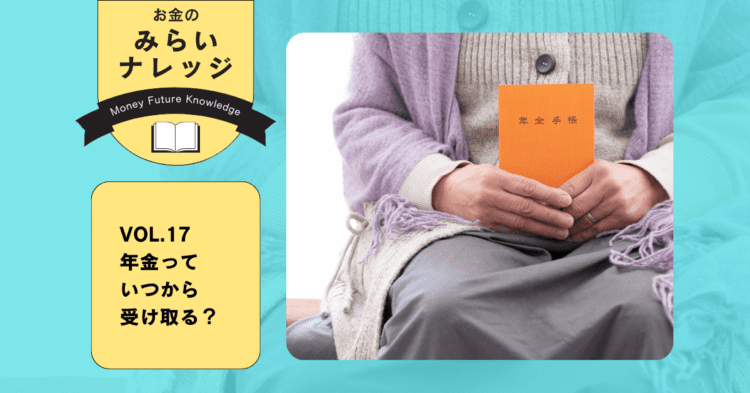
日本の公的年金制度は、老後の生活資金を支える大切な柱です。
原則として65歳から受給が始まる年金ですが、実は繰上げ受給や繰下げ受給といった制度を活用することで、受給開始年齢を60歳から75歳まで選択できるのをご存知でしょうか。
どのタイミングで年金を受け取るかは、受給額や生活設計、さらにはライフプラン全体に大きな影響を与えます。
ここでは、年金受給のタイミングについて、そのメリット・デメリットやリスク、さらには実際のシミュレーションを交えながら詳しく解説していきます。
受給開始年齢と仕組み
日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の2つから構成され、原則として65歳から支給されます。
しかし、年金は「申請主義」であり、受給開始時期を自分で選択できるため、60歳から繰上げ受給、または66歳以降の繰下げ受給が可能です。
繰上げ受給の場合、受給開始年齢を早めることによって、月々の年金額が一定の割合(生年月日によって0.4%または0.5%/月)減額されます。一方、繰下げ受給では、受給開始を遅らせるごとに0.7%/月の増額が受けられ、最長で75歳まで延ばすことができます。
たとえば、65歳で年金を受給する場合の基準額が200万円だとすると、70歳に繰下げると284万円、75歳にすると368万円といった増加が期待できます。
受給開始年齢ごとの特徴
繰上げ受給の特徴
繰上げ受給は、早期に生活資金が必要な場合に有効です。
例えば、60歳から受給を開始すると、減額率が毎月0.4%か0.5%(生年月日により異なる)となり、実際には受給額が大幅に下がります。具体例として、65歳で月15万円受給予定の方が60歳で受給開始すると、月11.4万円程度に減るケースが挙げられます。
| メリット | 早期に一定の収入を確保できるため、退職後の生活資金に余裕がない場合には安心感がある。 |
| デメリット | 生涯受給額が減少するため、長生きした場合には不利になる可能性がある。受給開始後は制度変更ができないため、一度決めると変更が難しいというデメリットも。 |
繰下げ受給の特徴
一方、繰下げ受給は、健康で長生きする見込みがある方や、受給開始までの生活費を他の収入や貯蓄でカバーできる場合に有利です。たとえば、65歳受給を基準に、70歳受給にすると42%、75歳受給にすると84%増額が適用され、受給月ごとの金額が大きくアップします。
| メリット | 受給額が増えるため、長生きした場合に生涯トータルの受給額が大幅に向上する。 老後の長生きリスクに備える有力な手段となる。 |
| デメリット | 受給開始までの期間、年金以外の収入や貯蓄で生活資金を補う必要がある。 万が一、健康上の理由などで早期に亡くなった場合、繰下げの恩恵が享受できず損をするリスクがある。 増額分は額面上の金額であり、税金や社会保険料の負担が増加する可能性がある。 |
受給タイミングの判断ポイント
年金受給開始のタイミングを決める際には、以下の4点が重要な判断基準となります。
1.健康状態
・自分自身の健康状態や家族歴、現在の体調を踏まえ、将来的な長寿リスクを考慮する。
・病気や重大な健康リスクがある場合は、早期受給を検討するのも一つの選択肢となる。
2.貯蓄状況
・年金受給開始までの無収入期間をどの程度カバーできるかが重要。
・十分な貯蓄や他の収入源があれば、繰下げ受給による増額メリットを享受できる可能性が高い。
3.65歳以降の収入
・退職後もアルバイトやパート、再就職などで収入がある場合は、早期の年金受給に依存しなくても良い。
・逆に、65歳以降の収入が不安定な場合は、早めに年金を受け取ることで生活資金の確保が必要。
4.家族や周囲のサポート
・配偶者や家族の収入・資産状況、またはサポート体制によっても、受給開始のタイミングは変わってくる。
・たとえば、配偶者がしっかりと収入を確保している場合、無理に早期受給をする必要はなく、繰下げによる増額を狙える。
これらの判断ポイントを総合的に勘案して、自身のライフプランに合った受給開始時期を選択することが、後悔のない年金設計につながります。
シミュレーションで考える受給タイミング
具体的な例で考えてみましょう。たとえば、65歳で月15万円、年間180万円の年金を受給するケースを前提にします。
さらに、受給開始時期と生涯受給総額との「損益分岐点」も考慮する必要があります。たとえば、70歳受給の場合、約81歳11ヶ月までに受給総額が65歳受給と同額になるとされています。長生きすることが前提となるため、平均寿命や自分自身の健康、生活設計を慎重に見極めることが重要です。
ケース1:繰上げ受給
60歳で受給開始する場合
→ 1ヶ月あたり0.4%の減額×60ヶ月=24%減
→ 月受給額は約11.4万円(年間約136.8万円)となる。
→ 早期に受給できる反面、長期的には受給総額が減少。
ケース2:標準受給
65歳で受給開始する場合
→ 基本額の月15万円(年間180万円)
→ 長寿であれば、生涯受給総額としてバランスが取れている。
ケース3:繰下げ受給
70歳で受給開始する場合
→ 1ヶ月あたり0.7%の増額×60ヶ月=42%増
→ 月受給額は約21.3万円(年間約255.6万円)となる。
→ 受給開始までの生活資金の確保が課題となるが、長生きすれば大きなメリットに。
さらに、受給開始時期と生涯受給総額との「損益分岐点」も考慮する必要があります。たとえば、70歳受給の場合、約81歳11ヶ月までに受給総額が65歳受給と同額になるとされています。長生きすることが前提となるため、平均寿命や自分自身の健康、生活設計を慎重に見極めることが重要です。
年金以外の老後資金対策
年金受給額を最大化するための方法として、年金制度自体の工夫だけでなく、公的年金以外の資産形成も視野に入れることが大切です。マネックス証券メディアの記事では、私的年金制度(国民年金基金や付加年金)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、さらにはNISAなどの資産運用による老後資金形成の重要性が指摘されています。
【私的年金制度】
・国民年金基金や付加年金は、加入条件や掛金のメリットがあり、年金額の上乗せ効果が期待できる。
【iDeCo】
・掛金が全額控除対象となり、運用益も非課税となるため、老後資金の効率的な形成が可能。
【NISAなどの資産運用】
・長期投資によって複利効果を狙いながら、税制上の優遇措置を活用し、余裕資金を増やしておくことで、年金受給とのバランスを取ることができる。
これらの制度を上手に組み合わせることで、年金の受給タイミングに左右されず、安心して老後を迎えるための資金計画が立てられます。
最適な年金受給タイミングを見極めるために
年金受給のタイミングは、一概に「これが正解」とは言えず、各人の健康状態、貯蓄状況、退職後の収入、そして家族のサポート体制など、さまざまな要素を考慮する必要があります。
・早期受給(繰上げ)は、短期的な収入確保には有効ですが、生涯受給総額が減少するリスクがある。
・繰下げ受給は、健康で長生きする見込みがあり、また受給開始までの生活資金が十分に確保できる場合、非常に有利な選択肢となる。
・また、年金だけに依存せず、私的年金やiDeCo、NISAなどを組み合わせた総合的な資産形成が、老後の安心につながる。
最終的には、自身のライフプラン全体を見据え、将来のリスクとメリットを天秤にかけた上で、最も適した受給開始時期を選ぶことが求められます。専門家と相談しながら、シミュレーションを重ね、情報をアップデートしていくことが、後悔のない年金設計への第一歩です。
以上のように、年金受給のタイミングは単なる数字の問題ではなく、人生設計全体に影響を与える重大な判断です。老後の安心と豊かな生活を実現するために、今一度、自分自身の状況と将来設計を見直し、最適な選択をすることが大切です。
関連するコラム
-

View More
2024.11.29
お金のみらいナレッジ
人生100年時代!定年退職後に安定収入を得るには?|お金のみらいナレッジ
近年、「人生100年時代」という言葉を耳にする機会が増えているように感じます。
皆様も… -

View More
2024.11.22
お金のみらいナレッジ
初心者必見!不動産投資を徹底解説|お金のみらいナレッジ
不動産投資は、資産形成や安定した収入を得る手段として近年注目を集めています。
一方で、… -

View More
2024.12.06
お金のみらいナレッジ
株式投資と不動産投資の違いとは?|お金のみらいナレッジ
資産運用の方法として、多くの人が選択肢に挙げる「株式投資」と「不動産投資」。
それぞれ…